- blog
- album
- (089)952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2024年1月27日 土曜日
今週は強い寒波が到来し、雪がちらつく日もありましたが、子ども達はそんな寒さに負けじと元気いっぱい登園してきました。みつばっこハウスに引っ越してきて、寒いだろうからと、古森先生に用意してもらったホットカーペットやヒーターを使いながら部屋を暖かくして登園してくる子ども達を迎えています。




ぐっと冷え込んだ火曜日、寒いからお部屋で過ごそうかと思っていましたが、日差しが出ている時間を狙い思いきって遊ぎ場に行くことにしました。外に行くことが分かると急いで帽子を取りに行き、できないなりに自分でかぶったり、手伝ってもらってかぶったりして、保育教諭の周りに集まります。『お外に行くの?』『やったー!』という声が聞こえてきそうな表情で、ワクワクしている気持ちが伝わってきました。みつばっこハウスから遊ぎ場までの移動にもすっかり慣れた足取りで、我先にと遊ぎ場に向かいます。タイミング良く、幼稚園児たちは室内にいて遊ぎ場を広々と走り回ることができました。「きゃー!」とおもいきり大きな声を出し、おもいきり走り、解放感を味わう子ども達の様子に嬉しくなり一緒に走り回っていると身体もポカポカになりました。
また、木曜日は水曜日から始まった『お味噌汁作戦』のあたたかいお味噌汁を飲み、元気パワーいっぱいにして遊ぎ場へ遊びに行きました。この日はスポーツ教室をしていたので築山の横の幼児用のすべり台に行くことにしました。するとそこにはたんぽぽ組さんたちが遊んでいたので「一緒に遊ばせてー。」と仲間に入れてもらいました。すべり台に行くには横の坂道を上がらないといけません。「ここから上がるよ。」と言っても最初は芝山の斜面を登って行こうとする子もいましたが、たんぽぽ組さんたちが上がって行くのを見て後ろからついて上がって行くことにしました。まわりに目を向け、様子を見ながら遊び方を真似し、ちょっとした決まり事を守っている姿に感心しました。そして時間になり、またみんなで歩いて帰ります。なんだかすっきりしたような表情を見て少しの時間でもお日様の下で気持ちの良い空気を吸うのは大事なことだなと改めて思いました。
そんな今週、1番冷え込むと言われた水曜日に向けて火曜日に水を張ったままごとのお皿や容器を設置して帰りました。でも思うような氷にならずがっかり・・・。すると学童の三好先生が設置していた水が見事に凍っていて、「ひよこさん、遊んでいいよ。」と言って頂きました。半分水で半分氷のたらいの中を、不思議そうにのぞくと「みずー。」「こーいー?」と指でツンツン触り、冷たさにびっくりしたのかパッと手を引っ込める子もいました。そしてたらいの中から氷を取り出すととってもきれいなまん丸でびっくり!子ども達も保育教諭からも「わぁー!」と歓声が上がりました。興味津々の子ども達は触りたくて仕方がない様子で指でツンツンする子、手のひらをペタッとくっつける子、中には顔を近づけてペロッと舌を出す子もいました。
まだまだ寒い日は続きますが、寒いからこその遊びや経験を楽しめたらなと思います。室内で過ごすことも多くなると思いますが感染症対策をしっかり行い、室内での過ごし方を工夫していきたいと思います。
2024年1月26日 金曜日
一昨日と昨日は屋外遊ぎ場では気温が下がり、氷が凍るほど寒い朝でしたが、今日は少し日差しが暖かく、体調不良でお休みする子もポツポツ増えていることから登園した子どもから園庭で遊ぶことになり、サッカーや縄跳びをして元気に遊んでいました。
様々な遊びの環境がある中、子どもたちは自分の遊びたいものを見つけて楽しんでいました。ままごとコーナーにいたちゅうりっぷぐみのTちゃんは、さんさんらんどの裏の山の上に朝日が当たってキラキラ光ることに気付き、「あの上がキラキラしてる〜」と指差しました。「あっ本当だね〜」と古森先生が感動していると、今度は別の子が「あっ、あの上も〜」と指差したのは第2園舎の非常用滑り台の上でした。そうなのです。その部分に太陽の光が当たって輝いていたのです。ままごとで遊んでいる中、楽しい、嬉しいではなく、「きれい」と感じて表現できる年少児に驚きました。そして、一方サッカーコーナーでは朝、さんさんらんどに登園していた年長児と年少児が遊んでいました。
ぞうぐみのSちゃんは「年少さん、前はルール守ってなくて、ゴールキーパーとかいっぱいおってサッカーできんかったんやけど、今はできるんよね〜」と教えてくれました。それを聞いてからサッカーをしている様子をよく見てみると、年長チーム、年少チームに分かれてゲームをしていました。年長さんが強いんだろうなと勝手に思っていると、そのとき勝っていたのは年少チームで、ぞうぐみのSちゃんが「年少さん強いんよね!!」と言いながら一進一退の戦いをしていました。年長チームが最後に点を入れて、同点になった時点で年長さんは幼稚園に上がるバスが到着してゲームが終了となりました。「また、今度続きしようね!」と約束をして年長さんは幼稚園に上がって行きました。
少し前まではゲームが成り立たなかったのに、教師が入らなくても優しくルールを教えて、怒らず見守ってくれた年長さんのおかげで年少児もサッカーを楽しむことができるようになっていました。遊んでいる子どもたちの目は、みんなキラキラ輝いていて、「教師が教える」ではなく子どもたちは年長児と関わり、体験してルールや、やり方を習得していくのだと実感しました。地域での子ども同士の関わりが薄い分、幼稚園で年長児や他の学年の子どもたちと関わり、刺激を得ることで、子ども自ら「教師が教えられないもの」を身につけていくのだと実感しました。
コメント (「たくさん遊んで病気に負けないぞ!」さくら組 中村真衣 はコメントを受け付けていません)
2024年1月25日 木曜日
今日、年長児は卒園DVDの撮影がありました。みんなこの日に向けて言葉や歌を練習してきていましたが、感染症の拡大の中、年長クラスでも数名の発生がみられたことから今日の撮影は、大きくなったらの1人ずつの撮影とドローンを使って室内遊びを撮って頂きました。
この日のために将来の夢を一生懸命考え、「毎日、やりたいことが変わるんよね〜」と色々な職業を見つけては悩む子や粘土が好きだから「粘土でお皿を作る人になりたい!」と自分の得意なことを夢にする子など、大きくなったら何になりたいか話す子ども達の目はキラキラ輝いていました。
次に遊びの撮影です。自分達のクラスでそれぞれ自分の好きな遊びを楽しむ姿をドローンが撮っていきました。真剣な表情や溢れる笑顔などとても楽しい撮影となりました。ドローンをこんな近くで見たことのない子ども達でしたが、遊びに集中し、本当にいつも通りの様子が撮影出来たと思います。ドローンのプロペラがすごい速さで回っていて撮影が終わると「風すごくなかった?」と友達と話していました。
年長児達の遊びは特に3学期になってからぐんと高度になっていて、表現豊かで細工も細かく、驚くことばかりです。粘土で家を作ろうとしていたHちゃんはまず、家の間取りを考えて粘土を棒状にして部屋を作ると、ミニチュアの家具達を部屋の用途ごとに作って飾っていたり、積み木で遊んでいた子は、友達と街づくりをしてごっこ遊びをしていたり、廃材で作った卵を用意していたフライパンで焼くと焦げ目(裏面は焼き色)がついたりと奥が深く、とても面白い遊びばかりです。卒園まであと2ヶ月もありませんが、そんな子ども達のいいところをこれからも沢山伸ばしていってほしいと願うばかりです。
全員で幼稚園の思い出を唱和する撮影の練習では、自分のクラスの言葉を紙に書いて何度も練習する子や、幼稚園の行き帰りの車の中で復唱する子、中にはセリフを言うたびに「涙が溜まってくる〜」と想いを込めて言う子も見られました。
残りの撮影は後日になりますが、そんな子ども達と次の撮影まで1日1日を大切に楽しみたいと思います。
コメント (「大きくなったら何になる?」 ぞう組 大隅咲 はコメントを受け付けていません)
2024年1月22日 月曜日
初夏の頃になると、雨上がりの園庭で水たまりを見つけると、そこに入って水や泥の感触を楽しんでいた子ども達ですが、今朝は1月というのに陽だまりが暖かく、あまり冷え込んでいないこともあって、園庭に水たまりを見つけた子ども達は入ることこそなかったものの、水たまりで泥だんごを作ったり、泥遊びを楽しんだりする姿が見られました。自然の変化に敏感に気付き、それらに関わっていく子ども達に驚かされます。
さて先日、三葉幼稚園の果樹園で伊予柑狩りをした時に、沢山実がついた小さな細い木が一本ありました。小さく細い木には小さな小さな実がなっていて、そのみかんは食べても苦味があって、美味しくないということで、ままごとコーナーに出してくれました。それを見つけた子ども達は、包丁で半分に切ると、絞り器の中に入れて、上から押して次々と搾り出し、それをコップに入れたり、氷を作る器に入れたりして「先生 ジュースです」と持ってきてくれました。伊予柑の香りが漂っていて、本物のジュースができていました。この時期、このタイミングだからこそできる季節の今だけの本物を使った本物のジュースやお料理体験です。自園の果樹園や畑だからこそ、実った果物や野菜を選別して食べられる物と食べられないけれど捨てることなく利用して本物体験ができるのだと感動しました。
その後、発表会まで10数日、どの学年もそわそわ!外で遊んでいる時も発表会の曲がかかっていて、早めに片付けると各学年、各部屋で練習が始まります。小さいクラスでは、形から入ろうとお面を作り終えて、それを被ることで役になりきって演じ始めるのです。オペレッタでは出来ている大道具を使って、そこにスタンバイをして、動いたり、踊ったりして気持ちを高めていきます。プレさんは、嬉しそうに「うさぎ」とお面をつけて見せに来てくれて、とてもかわいかったです。オペレッタでは、海に落ちる場面があり、そこで何で海に落ちるんだろう?海に落ちたらどうなるのかなぁ?大きな波が来たらどうなるのかなぁ?と声をかけると、波が寄せてくる様子を表現して、動きがそれぽっくなってきました。
先日、園長が歌、劇等もしっかりイメージをもたせることが大切、特に今の子ども達は、おばあちゃんと言っても元気なおばあちゃんしかしないし、腰が曲がっているおばあちゃんはイメージできないことや雪を知らない子ども達に雪が降ってくる風景をイメージすることは難しいことを等など教えていただきましたが、本当にそうだなぁと思いました。発表会当日に向けて子ども自身がイメージをしっかりもって演じられたり、歌えたりできるようにしていきたいと思います。
踊り大好き・お歌大好きの子ども達の発表会、お楽しみに‼︎
コメント (「イメージを膨らませて」 ひつじ組 谷川幸実 はコメントを受け付けていません)
2024年1月20日 土曜日
みつばっこハウスに引っ越ししてから半月以上が過ぎ、子ども達は生活にも慣れてきました。
みつばっこハウスのトイレや手洗いは子ども達が使いやすいようにリフォームされていましたが、子ども達が使うロッカーは置かれていませんでした。私達保育教諭はカバンをなるべく端の方へ寄せて並べていたのですがそれを見た古森先生に「ロッカーはいくつあったらいいの?」とすぐ本園から運んで設置していただき、カバンも整理することができました。そして、「必要なものや足りないものは、その都度報告したり補充したりするのも保育教諭の役割」と注意を受けました。そして子ども達は、今ではすっかり住みやすく温かいみつばっこハウスの住人になりました。
子ども達はみつばっこハウスで、遊び慣れたレゴブロックやソフトブロック、ままごと、絵本など思い思いのおもちゃを使って遊んでいます。ソフトブロックは子ども達に大人気です。ある日、Tちゃんが平らにつないだブロックを持ってきて「これ見て♪」と畳の上に置いて見せてくれました。するとKくんが電車を持ってきて、Tちゃんがつないだブロックの上を走らせようとしたのです。しかし少しスペースが狭く思えたので「もう少し大きくする?」と声をかけると「うん!」と言って同じようなブロックを集め始めました。すると周囲にいた他の子ども達もひとつ、ふたつ、とブロックを集めて持ってきました。「これはここ!」「どこにする?」と子ども同士で話しながらブロックをつないでいきました。2歳になったばかりの幼児たちのその姿に驚くと同時に、頼もしく思えました。幼稚園児と関わることの多い子ども達は、2歳になると個々ではなく友達と協力しあうこともできるんだなと感心すると同時に、幼児の発達は環境が大きく左右することを実感しました。
庭に出る時も、くつを順番に履くとみんなを待つこともできるようになりました。また、ジャングルジムのブランコに乗りたくなったMちゃんは少し恥ずかしそうに「かーわって」と声をかけ、乗っていたAちゃんも「いーいーよ!」と交代してくれました。このようなやりとりができるようになっていることに改めて成長を感じました。
今年度は第二園舎での生活で幼稚園児とたくさん関わることができ、いろいろなことを学びました。友達とのやりとりも、お兄さん・お姉さんとの関わりから身についたことだと思います。私達保育教諭はそんな子どもの様子を見守り、まわりの環境に目を配ること、そして「できない」ではなく、「どのようにすればできるのか」を考えていかなければならないことを学んでいます。そして幼稚園の先生達から工夫次第でどのようにでもできることを教わり、園長からは幼稚園と同じようにたくさんの指導や援助をしてもらっています。何よりも日々、子どもたちとの生活の中で気づいたり学んだりすることもたくさんあるので、これからも保育教諭として子どもとの関わり、見守り、援助のタイミングなど三葉の保育の連続性を大切にしていきたいと思います。
コメント (みつばっこハウス楽しいよ ひよこ れもん組 檜垣 美恵子 はコメントを受け付けていません)
2024年1月19日 金曜日
今日は松山市移動図書の日。今までは山西団地へ借りに行っていたのですが、今月から第2園舎へ特別にきてもらえることになりました。久しぶりの移動図書の貸し出しに子ども達はとてもワクワクして屋外遊ぎ場へ出発しました。「なに借りようかなぁ」「恐竜の本あるかなあ」などと話しながら歩いていきました。
さんさんらんどに着いてから少し時間があったので、雨上がりの水溜まりで泥団子を作ったり、ジャングルジムやドームに上ったりと体をいっぱい使って遊んでいると、椿号が入ってきました。子ども達は目ざとく見つけて、「あっきた!」と嬉しそうな笑顔で立ち上がり、駆け出しました。そして、「おはようございます!」と元気いっぱい挨拶をしてから貸し出しスタートです。子ども達は、自分が読みたい本を決めていて、真剣な表情で探して見つけると、「あった!」と目をキラキラさせながら宝物を見つけたようにパァと笑顔になっていました。今までの習慣で、しっかり挨拶をすること、絵本のバーコードと自分のカードを合わせて持って出すことなど、みんなマナーを守って借りることができました。又、料理の本を探している子には、椿号の職員の方が「こんな美味しそうな本があるよ」「これならみんなも作れるかも」と子どもがとびつくような素敵な絵本を探してくれました。三葉幼稚園の子ども達のための特別出張図書館なので、ゆっくり探して気に入った本をペラペラめくりながら「面白そう」と会話もすることができてすごくいいなと思いました。誕生日占いの本を借りたᏚちゃんは、本園に帰ってから園長の誕生日のページを開けて占っている姿もありました。
午後、保育終了後預かり保育中、「年長さん、大林組さんからヘルメットもらったよ!おりておいで~」と園長の放送がかかりました。子ども達と急いで事務所まで行くと大きなダンボールがありました。箱をあけてびっくり!大林組さん特製の子ども用のオレンジ色のヘルメットが30個入っていました。前は紐、後ろはプラスチックのベルトで頭を固定できるようになっていて、まるで本物で、A君がまず被ってみるとピッタリでよく似合っていて驚きました。みんなが順番に被ってみながらいつも工事をしてくれている憧れの大林組さんと同じヘルメットを被ることができて大喜びしていました。そして、「ちから・ちから・ちから!」が合い言葉になっている年長児は、自然とポーズをとって気合いを入れていました。ツルツルピカピカ、叩いても痛くないヘルメットは、みんな気に入り、交代しながら被ると鏡の前に行ってチェックし、お互い「かっこいいね」と褒め合っていました。大林組さん、大谷選手のグローブならぬ、大林組ヘルメットを子ども達の為にありがとうございました。
コメント (『椿号がさんさんらんどにきたよ!』 きりん組 岸田亜寿美 はコメントを受け付けていません)
2024年1月18日 木曜日
今日は、さんさんらんどの果樹園の伊予柑をみんなで収穫しました。最初に、年長と年中が果樹園にあがり収穫をしました。収穫する前に、古森先生からたくさんの話をして頂きました。「今日収穫するみかんの名前が“ 伊予柑”と言う名前で、愛媛県は昔、伊予の国と呼ばれていたんだよ」と教えてくれました。「伊予って名前が付いているから愛媛のとっても美味しいみかんなんだよ」と話してくれているのを真剣に聞いていました。さらに、「ここの果樹園のみかんは山の上からあたる太陽の光と海から来る風が吹いてとっても美味しいみかんだからね」と、教えてくれました。子どもたちはそんな美味しいみかんを自分で収穫できると知ると、さらに笑顔になっていました。
まずは、年長さんから収穫します。年長さんは身長も高いので年少さんのために上の方の伊予柑を収穫することになりました。その前に、年長さんたちはこっそり、古森先生から「上の方の伊予柑は太陽の光が沢山当たってとっても美味しいよ」と教えてもらっていたので、高いところにある伊予柑を採ろうと、手を一生懸命伸ばして採っていました。1人1個収穫し、幼稚園から持ってきていた緑カバンに大切に入れていました。まずお土産用に1個採って、味見用に5人で1個を分けっこして採れたての伊予柑をもらいました。分厚い皮をみんなで協力して一生懸命剥いていました。皮を剥き終わると、みんなで味見の時間です!子ども達は、薄皮も上手に剥いてペロリッと食べていました。そして「美味しい!」と、とってもいい笑顔になっていました。
手を洗ったあとも、手の匂いを嗅いで「まだ伊予柑の匂いがする〜!」と何度も香りを楽しんでいました。大きい組のお兄さんお姉さんがみかんを採りに行くのを聞いて年少さん、たんぽぽさんも急いで準備をして果樹園に上がり、小さい手を大きく開いて両手でクルクルして伊予柑を収穫しました。そして、「先生見て!伊予柑採ったよ!」と、とっても嬉しそうに見せてくれました。
収穫も終わりしばらくすると、子ども達に嬉しいお知らせが!!!
なんともう1個、お土産で持って帰れると放送があったのです!それを知った子ども達は大喜び!!すぐにカバンの中に、もう1個もらって入れていました。降園の時にもカバンを前にしてカンガルーのように持ち、大切に持って帰っていました。「みんなで分けっこして食べるのが楽しみ!」と早く家族に見せたくて仕方ない様子でした。ご家族みんなで、みかん狩りの話を聞きながら、召し上がってください。採りたてなので少し酸味が強いと思います。
今日1日とっても美味しくて、とっても楽しい経験をした子ども達。伊予柑パワーで発表会の練習も頑張ります!
(実はまだ幼稚園には伊予柑が残っていますので、練習の後、ご褒美でみんなで頂きます。)
コメント (「伊予柑狩りをしたよ!」 うさぎ組 西川友理 はコメントを受け付けていません)























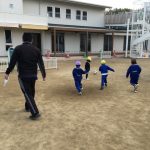
































































コメント (「やっぱりお外が大好き!」 ひよこ みかん組 山岡由紀子 はコメントを受け付けていません)