- blog
- album
- (089)952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2019年10月2日 水曜日
送迎バスに乗っていると、田んぼや畑のあぜ道に咲くヒガンバナの赤色が目に飛び込んできます。
園の駐車場の片隅にもそっと咲いて、秋の風にゆれています。畑に秋茄子が実り、テラスに持ってくると、たんぽぽ組の子どもたちが触ったり匂ったりしていました。ぱんだ組の子どもたちに、茄子でどんな料理ができるかな?と聞くと、「しょうゆつけて食べる」「焼肉みたいに焼く」などと言っていました。よく見ていますね。
同じくテラスには、種がいっぱいつまったひまわりが置いてあります。子どもたちが一粒一粒取り、並べて数を数えていましたが、数えくれないくらいの量で、箱いっぱいになっていました。
ひめあちゃんの一粒の種から花が咲き、たくさんの種ができました。「ひめあちゃんは、こうやってみんなに種を分けてあげたかったんだね」と子どもたちに話すと、じっと見つめてうなづいていました。命のつながりを感じてほしいと思いました。
さて、今日は3か月ぶりの家庭弁当日でした。登園時、「お母さんのお弁当が入ってるからカバンが重た~い」という嬉しい悲鳴が聞こえてきました。また、泣いてぐずっていた年少さんに「カバンにお弁当が入っているからね」とお母さんが声をかけると、すっと歩いて行くことができていました。
お弁当の時間には、「ウインナーある人~」「は~い」「ぼくのは、カニさん」など楽しく会話していました。運動会の練習をがんばった後のお弁当は、一番のごほうびとなりました。
今、職場体験で三津浜中学校の生徒さんが来ています。子どもたちと一緒に砂場で穴掘りをしたり、得意な絵を描いて見せてくれたり、ひつじ組のTくんは、バッタの絵を描いてもらい、嬉しくてそれに色を塗っていました。子どもたちも年齢の離れた人とかかわる経験ができています。
2019年8月29日 木曜日
今日は、赤コースの夏期保育でした。子ども達は久しぶりに会った友達と戸外に出て、砂場や包丁ままごと、ブランコなど一学期に遊び慣れた所へ行って、笑顔で会話しながら遊んでいました。また、教師が広々とした園庭にラインを描き始めると、年長児が走り始め、それを見た年中児も加わり「よーいどん」でかけっこを楽しみました。担任の教師が走り始めると、一緒に走るのも嬉しい様子で、年長児は競い合うことを楽しみ、年中児は、「先生頑張って」と応援していました。遊びの中で、思い切り体を動かし、競い合い、応援することを楽しみながら、二学期の運動会に気持ちがつながっていくといいなと思います。
さて、朝から「かき氷やさん」に気づいて、気になっていた子ども達と準備中のお店を見に行きました。古森先生が「かき氷食べたい人~」と声をかけて下さり、「はーい!」と次々に手を挙げました。お金はいくらかな?どんな味があるのかな?とお店の貼り紙を見ていると、「お店の人してみる?」とまたまた古森先生が誘って下さり、お店の人役、お客さん役になって、「いらっしゃいませ、かき氷いかがですか」「いちごをひとつください」「30円です」「はいどうぞ」「おいしかったよ」「ありがとう」と準備中の店内でかき氷やさんごっこをすることができました。それぞれの立場に応じた言葉でやりとりをすることを知り、経験することができました。そして、本物のかき氷を買うことに大きな期待をもって、お金作りをしました。お金にはどんな種類があるのか、硬貨と紙幣の種類を子ども達に聞くと、知っているものを答えていました。自分で作ったお金で、好きな味のかき氷を買って食べることができ、かき氷を作ってくれた先生たちにお礼を言いました。Rくんは、「ほっぺが落ちるくらいおいしかった」Kくんは、「バナナが凍ってた」と感じたことを言葉や仕草で表現していました。
降園前に、りす組では夏休みの思い出を子ども達に聞いてみました。「水族館に行ったよ」という子が多く、「何を見たの?」と聞くと、「カメ」「ペンギン」「クラゲ」と答え、Aちゃんに、カメはどのくらいの大きさか聞くと、「これくらい」と顔の大きさくらいを手で表現して教えてくれました。名古屋に行ったというAくんに、どうやって行ったか聞くと、「飛行機に乗った。電車に乗った。バスにも乗った。」といろいろな乗り物に乗ったことを話してくれました。Rくんは、島の海に遊びに行ったので船に乗ったこと、Kくんは、砂浜で穴を掘ったら水が出てきたこと、一人ずつ話を聞いていると、次々に手が挙がり、自分も話したいという子がたくさんいました。経験したことや感じたことを言葉で伝えることの楽しさ、それを人に聞いてもらえる喜びを感じていけるといいなと思いました。
コメント (言葉で伝え合う喜び りす組 佐々木 恵 はコメントを受け付けていません)
2019年6月27日 木曜日
今週は、月〜水の3日間、自由参観日でした。戸外遊び、クラスでの活動などいろいろな場面を見て頂きました。中でも、プール遊びは子どもたちはもちろん、保護者の皆様も楽しみにされていたことと思います。実は、当日プール室の室温、水温は低く、普段なら入れない日でした。戸外は気温が高く、日差しも強く、汗もかいてプールに入れてあげたいと思うものの「どうする?」と悩んでいました。そこで古森先生が“ストーブをつけて、プール室の室温を上げる”という考えてもみなかったアイデアを出して、すぐに準備してくださったのです。プール室の室温が22℃、水温23℃、外気温28℃であれば、プール室の室温を上げて外気温と同じにすれば、水温が低くても気持ちいいし、出た後も寒くないでしょうと教えてくださいました。そして、その結果、気持ちよく水に入り、子どもたちは「キャーキャー」と歓声をあげて水遊びを楽しむことができたのです。
私たち教師は、つい“出来ないから仕方ない”と諦めてしまいがちなのですが、古森先生は、“どうすれば出来るのか”を常に考えて、身をもって私たちに教えてくださいます。子どもの姿を見て、どういう遊びをしているのか、なぜそうしているのかを考えること、教師が子どもに経験させたいことがあるなら、どういう環境作りをすれば良いか考えること、繰り返し私たちに示してくださっています。現代は、多様性の時代と言われます。どんな状況になっても「どうすれば出来るか」という考え方を身に付けておくことは、これから生きていく子どもたちにとっても大切なことだと思います。
今日は朝から大雨で、プールの前の海の家では、テントの隙間から雨が落ちていました。雨水を受けるために、教師が足洗いのたらいやバケツを置いておくと、どんどん雨水がたまっていきました。雨が降るし、濡れるから、いつもござを敷いてブロックなどで遊んでいたのですが今日は出来ないと思ってきたところ、またまた古森先生が来て、小さなプレ年少たんぽぽ組の子どもたちと「ジャンプ、ジャンプ」と一緒に飛び跳ねて遊び始めました。人工芝の下には水を含んだ土があるので「グジュグジュ」と足で踏むと水が出てきてその感触を楽しんでいました。たらいにたまった水を手でちゃぷちゃぷしてみたり、水くみ遊びで使っていた廃材のカップや容器を出してくると、たらいから別のたらいへ水を運んだり、テントの屋根からポタポタ垂れてくる雨の雫を受けたりしていました。ここでも、雨の日だからこそ、何が出来るかを考えることなのです。たんぽぽ組の子どもたちは、ずっとこの遊びを楽しんでいました。
さて、りす組の子どもたちは、すみれ組におもしろい物があるということで遊びに行きました。すみれ組のYくんのおじいちゃんが、木でビー玉転がしの板を作ってプレゼントしてくれたそうです。3つあり、りす組の子どもたちが自然に3つのグループに分かれました。グループ①は、リーダーになる子が出てきて「僕の後ろに並んで」と言い、順番を待って遊んでいました。グループ②は、貸し借りが上手くできず、自分がしたいと主張が強くてけんかになっていました。グループ③は、椅子の座面に立てかけていた板を座面の上に置いて、自分たちで傾斜の角度を変えながらビー玉が転がるスピードの違いに気付いていました。年少のすみれ組の子どもたちが遊んでいた様子と年中児の違い、グループごとの違いを見て子どもっておもしろいなと思いました。
健康情報…結膜炎になっている子どもが増えています。西日本では、手足口病が増加しているというニュースもあります。手洗いをしっかりしましょう。
コメント (できる?できない? りす組 佐々木 恵 はコメントを受け付けていません)
2019年6月3日 月曜日
雨上がりの今朝、しゃぼん玉コーナーでは、子どもたちが吹くストローの先から、しゃぼん玉が次々に空高く上がっていく様子がみられました。スタンプコーナーでは、異年齢児たちが関わりながら、ペーパーを繋いでいき線路が長く伸びて、電車や家もできて素敵な町ができていました。また、お家からてんとう虫の抜け殻を持って見せてくれたり、黒い幼虫が、ビオラの花を食べることを知ると、咲き終わってしおれたビオラの花を入れて食べるかどうか観察するなど生き物への興味・関心が広がっているようです。
さて、今日はプレ年少、年少、年中の子ども達は、じゃがいも掘りに行きました。古森先生が「誰が植えたのか知ってる?」と聞くと「年長さん!」と答えた子がいました。今の年長児が年中の時に種いもを包丁で半分に切って切り口に灰をつけて植えたものです。1株に何個おいもができているか数を数えた後、古森先生が「お母さんおいもですか?」とおいもに聞くと「違いまーす、僕はお兄ちゃんおいもでーす」と1つ1つのおいもに聞いていくとどれも違いました。最後に、半分に切れた黒くてしわしわになったおいもが出てきて、「はい、私がお母さんおいもです」子どもたちにいっぱい栄養をあげてしわしわになったお母さんおいもに「ありがとう」と言って、畑に返してあげようねと話してくれました。畑の土はとても柔らかく、子どもの手でも簡単に掘ることができていました。自分で1株掘って、出てきたおいもを並べて「7人家族だった!」「私は3人家族」など、話を聞いていた子どもたちは、そう言って数を数える姿がありました。おいもを落とさないように両手で抱えてそっとキャリーに入れていきました。
青コースの子どもたちは、秀野邸内を探検しました。古森先生がお殿様役になって「何をしに来たのじゃ」と尋ねると、「じゃがいもを掘りに来ました」と子どもたち。長いやりを見せてくれて、沢山発見があったようです。赤コースの子どもたちはお庭を探検して、どんぐり拾いや落ち葉遊びを楽しみました。
今日みんなで掘ったじゃがいもは、プール開きの日にカレーライスになってみんなの所に帰ってきます。
暑い中、お手伝いに来て頂いた役員さんありがとうございました。
今日、年長児は今朝6時に三津浜港に入港したダイヤモンドプリンセス号、豪華客船を見に行きました。市役所観光課に連絡をとり、園バスをすぐ近くまで入れる許可を特別に頂き、間近で見学させて頂きました。15階建てで見上げても見上げきれないほど大きな船に子どもたちは大興奮でした。「すごーい!」「かっこいい!」「未来みたいだ!!」と口々に話す子どもたち。目を輝かせる三葉っ子たちに海外からのお客さんが次々に“Hello!” “Hi”と話しかけてくれました。(三葉っ子こ可愛さは万国共通です!)そんな海外の方にも「ハロー!」「シーユー!!」「サンキュー!」と声をかけると、外国人の乗組員の方が「アリガトウゴザイマス」と答えてくれました。その場その場で見事に受け応えする三葉っ子たちに、教師たちは嬉しいやら感心するやら“さすが!“の一言です。今日はいい経験になりました。身近にある、こんな環境もどんどん利用していきたいです。
コメント (「じゃがいも掘りに行きました」 りす組 佐々木 恵 はコメントを受け付けていません)
2019年5月9日 木曜日
昨日のブログの中で、年少さんがフラフープを使って、お引越しゲームをしたという話がありました。今日も園庭の真ん中に、古森先生がポン、ポンとフープを置いてくれました。一つ一つの輪を、両足そろえてピョン、ピョン跳んで進んでいると、登り棒の所にあった巧技台やタイヤが、途中に入ってきて、少しずつ難易度が上がって、おもしろくなってきました。そうしているうちに、今度は、大きな丸太が途中に転がされ、その上を歩くとグラグラ動くので、みんなびっくり。恐る恐る渡っていきます。古森先生が、やって見せてくれると、子どもたちも次々に挑戦していきました。初めは、年長児が多く並び、難易度の高い丸太の上を進んでいきました。フラフラしながらも、両手を広げてバランスをとり、足を一歩ずつ前に出していく子、身体を横向きにして、カニさん歩きで足を滑らせながら進んでいく子など、どの子も意欲的に取り組み、順番を待つ列もどんどん長くなっていきました。
遊び一つで、自主的・主体的に行動し、目標を持って取り組むようになり、楽しむためには、きまりを守ることも自然に経験することができていました。そして、「〇〇がないからできない」ではなく、「何か使える物はないか」という考え方も、これから生きていく上では、とても大切なことだと思いました。
今日は、そんな楽しい遊びもあったことから、遅コースのバスが着いた後には、ほとんどのクラスの子どもたちが、戸外で遊んでいました。すると、「お引越しゲームをしようか」と古森先生が、小さな年少さんの手をとり、フープの中に入りました。音楽が始まると、教師たちも集まり、クラスに関係なく「おいで、おいで!」とあちこちに小さな輪がたくさんできました。二回目は、人数を増やしていこうと「1人から2人になって、どんどん増えて50人の輪ができたらすごいよね~」という古森先生の呼びかけでスタートすると、最後はみんなで一つの輪になりました。
10連休という長い休みが明けて、年少さんの中には、泣いて登園する子がいたのですが、今日は、楽しい環境ができたことで、泣いていた子も遊ぶようになりました。教師たちが、考えもつかないアイデアを古森先生が出してくれて、入園して1か月の子どもたちを助けてくれました。何よりも、小さな子どもたちが、古森先生の周りにたくさん集まって、笑顔になっていく姿を見て、子どもたちが、今、必要としていることは何か、そのために環境はどうするべきか、教師のかかわり方はどうあるべきかを考えることができました。
今日の手作り給食には、アルミホイルに包まれたものがあり、「なにが入ってるの?」と子どもたちは、わくわくしながら開けていました。「おさかな!」と喜んで、みんな残さず食べました。お手伝いしてくださったお母さんたち、ありがとうございました。
コメント (なにして遊ぶ? りす組 佐々木 恵 はコメントを受け付けていません)
2019年4月12日 金曜日
園庭に咲き誇り、春の訪れを知らせてくれた桜の花も、今朝は風に乗って舞い散っていました。砂場の周辺では、足を踏み入れるのをためらうほど、美しいピンクのじゅうたんが広がっていました。登園した子どもたちは、風に舞う花びらと競争して走ったり、両手ですくって息を吹きかけて飛ばしたりして遊んでいました。
昨日、入園後初めての登園日となった年少さんの子どもたちは、担任の先生と一緒に包丁ままごとコーナーで野菜を切っていました。硬くて切りにくいかぼちゃを、扱いやすい大きさに教師が切っておくと、それをどんどん小さく切って「いっぱいきったよー」と嬉しそうに見せてくれました。
年中・年長になった子供たちは、昨年経験している色水遊びを楽しみ、「こんな色ができたよ」と見せてくれて、水を多くしたら水色になったこと、にんじんで作ったからオレンジ色になったことなど、どのように作ったかを話すことができていました。すり鉢と棒の数が限られているので、順番を待つこともできていました。
さて、幼稚園の駐車場にも春がやってきました。毎朝、畑の様子を見てくださっていた古森先生が、「スナップエンドウができているよ」と教えてくれました。早コースの年長くま組ときりん組のこ子どもたちが取りに行きました。古森先生が採って見せてくれた豆は開くと中の種が左右のさやに交互にくっついていました。どんなに振っても落ちない種は、栄養をもらうためにしっかりとつながっていることを知りました。根から入った栄養が、どんどん上に上がってきてここまで来るんだねと教えてもらいました。一人一つ採り、自分が採ったものと友達が採ったものとを比べて、大きさや膨らみ具合、形、長さなどの違いに気付き、話す姿がありました。その隣にはビワの木があり、緑の実がたくさんなっていました。大きな葉に守られている実もこれからどんどんオレンジ色になっていきます。アスファルトからタケノコが顔を出し「このままだと駐車場がボコボコになる!」と叫ぶ子もいました。いろんな発見をした畑を後にする時、りす組のKくんが「畑は楽しいことがいっぱいだね!」と満面の笑みで話していました。
私たち教師も自然に親しみ、自然と共に育っていきたいと思いました。
コメント (「春の発見」 りす組 佐々木恵 はコメントを受け付けていません)
2017年10月19日 木曜日
今朝は雨。雨の中、子どもたちを迎える準備をした後、昨日年中児が刈った稲を干しているとからすが狙っていることに気付き、網をかけていました。それを見て園長が雨のしずくがかからないようにとテラスの上に円椅子を置いて移動してくれました。太陽のパワーで乾いたら、みんなでお米の服(もみ)を取っていこうと思います。そして穂を取った藁で縄を編んだり、草履を作ったりしてみたいと思います。
一方、お部屋では、廃材遊びを楽しんでいました。宇宙プロジェクトで宇宙に行くロケットに興味を持っていたA君は、アルバムにもロケットの絵を描いて貼っていました。数日前からペットボトルが廃材箱にあるのを見つけたA君は、それを持ってクレヨンでペットボトルの先を塗り始めました。根気よく何時間も、服が赤く染まるほど頑張っていました。その次の日は、気に入った色々な形の箱を見つけ、それを組み合わせペットボトルをくっつけるとロケットが出来上がりました。そして「発射するところ」と言って、「10、9,8,7、・・・・」と数を数え始めました。「発射台があるといいかも」と声をかけると、すぐに作り始めました。一学期は牛乳パック4つをくっけて、「ピストルなんよ」「ここからも ここからも玉が出るんよ」と教えてくれました。そんなA君が今日は何日もかかって、自分がイメージしたものを考えて、根気よく最後まで作ったので、成長を感じ、とても嬉しく思いました。
それに刺激された他の子どもたちも思い思いのものを作り始めました。B君は「僕もロケットの発射台を作ろう」と言って、ロケットになる物を見つけると、それを立てて「ロケットに乗る階段がいるよね」と言って、牛乳パックを切って階段を作っていました。
一人一人が自由に自分でイメージして工夫しながら表現した作品が、お部屋に増えてくるのがとても楽しみです。
今日は、全園児、手作り給食でした。
コメント (廃材遊び 大好き!! りす組 谷川幸実 はコメントを受け付けていません)




































































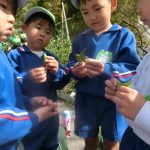













コメント (秋らしくなりました りす組 佐々木 恵 はコメントを受け付けていません)